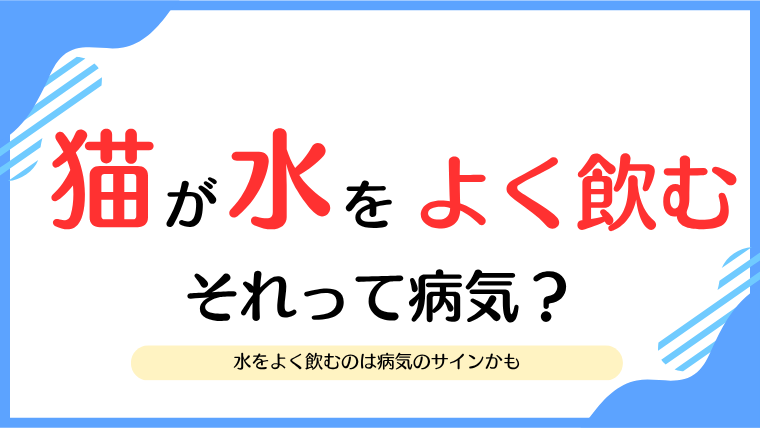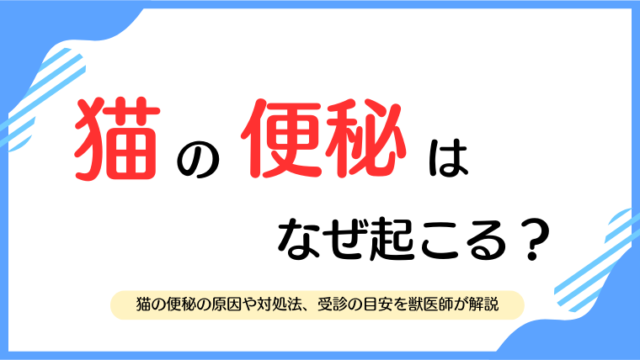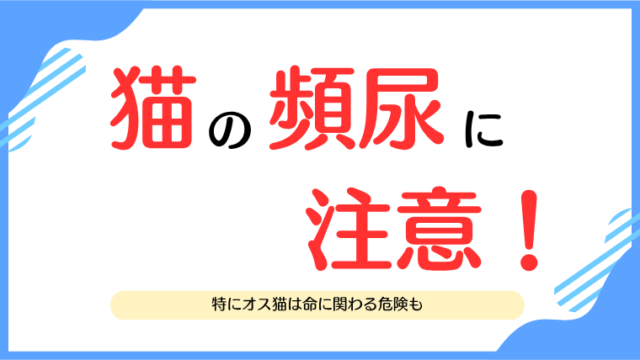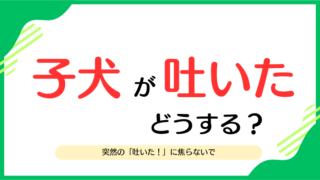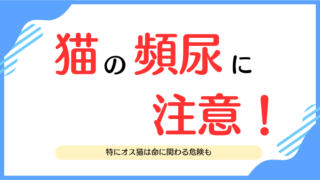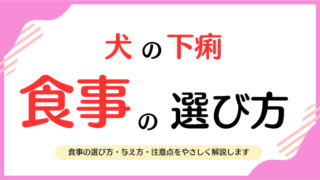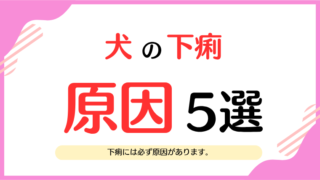「最近うちの猫が水をたくさん飲む気がする」
「前より頻繁に水皿に顔をつけている」
そんな変化に気づくと、ちょっと心配になりますよね。
猫はもともと水をあまり飲まない動物です。
だからこそ「急に水をよく飲むようになった」という変化には、体からのサインが隠れていることがあります。
もちろん、気温や食事で一時的に増えることもあります。
でも、病気の初期症状として増えるケースも少なくありません。
この記事では、猫が水をよく飲む理由、受診の目安、おうちでできるケアを、獣医師の視点で分かりやすくまとめます。
先に結論
「急に増えた」「おしっこも増えた」なら、一度検査を考えてください。
猫が水をよく飲むとき、いちばん大事なのは「いつもより増えたかどうか」と「他の変化があるか」です。
特に次の2つがそろう場合は、病気が隠れている可能性が高くなります。
✅ 飲水量が急に増えた
✅ おしっこの量・回数も増えている
このタイプは、腎臓病や糖尿病などが早期に見つかることも多いです。
「元気そうに見えるから大丈夫」と決めつけず、早めに確認しておくと安心です。
正常な飲水量の目安を知ろう

まずは「どのくらい水を飲むと多いのか」を知ることから始めましょう。
一般的に、猫の1日の飲水量の目安は、体重1kgあたり40〜60ml程度 といわれています。
たとえば、4kgの猫なら 160〜240ml前後が目安です。
ただし、ここで注意したいのは「すべての水分」には食事からの水分も含まれることです。
ウェットフード中心なら、食事から水分を取れるので、水皿から飲む量は少なくなります。
ドライフード中心だと、フードの水分が少ないため、水皿から飲む量が増えやすいです。
また、季節でも差があります。
夏の暑さ、冬の暖房による乾燥などで、自然に飲水量が増えることもあります。
ポイント
✅ 「急に増えたかどうか」が重要
✅ 元気・食欲・排泄が普段通りなら一時的な可能性もある
✅ 気になるときは、1日の飲水量を実際に計ってみる
猫が水をよく飲む主な原因

水をたくさん飲む理由は、大きく2つに分かれます。
✅ 生理的な原因(正常範囲内)
✅ 病気によるもの
ここから順番に見ていきましょう。
① 一時的な生理的な原因(正常範囲内)
次のような状況では、一時的に飲水量が増えることがあります。
✅ 夏の暑さや乾燥した環境
✅ ドライフード中心の食事
✅ 活動量が多い、運動後
✅ 遊びの延長で水に興味を示す(舐める)
この場合、猫の体の調整として自然な範囲のことも多いです。
元気・食欲・排泄が普段通りなら、過度に心配はいりません。
ただし、
「前は飲まなかったのに急に増えた」
「おしっこも増えている」
この変化があるときは、次の「病気の可能性」を考えましょう。
② 病気による飲水量の増加
猫が「急に」「明らかに」水をたくさん飲むようになった場合、次のような病気が隠れていることがあります。
ここからは、特に多いものを中心に説明します。
②ー1慢性腎臓病(猫でとても多い原因)
猫に最も多い原因のひとつです。
腎臓は老廃物をろ過して尿を作る臓器ですが、加齢や体質で少しずつ働きが弱っていくことがあります。
腎臓の機能が落ちると尿が薄くなり、体の水分が逃げやすくなります。
その結果、喉が渇いて水を飲むようになります。
特に 7歳以上の中高齢猫は要注意です。
初期は元気に見えることも多く、健康診断で見つかるケースもあります。
②ー2糖尿病(よく食べるのに痩せる+多飲)
「よく食べるのに痩せてきた」
「水をたくさん飲む」
こんなときに疑う病気です。
血糖値が高い状態が続くと、尿に糖が出ます。
そのとき水分も一緒に排出され、喉が渇きやすくなります。
治療が遅れると、脱水や意識障害など命に関わることもあるため、早期発見がとても大切です。
②ー3甲状腺機能亢進症(高齢猫に多い)
高齢猫で見られる病気で、代謝を調整するホルモンが過剰に出ることで起こります。
✅ 落ち着きがなくなる
✅ よく食べるのに痩せる
✅ よく動く、夜鳴きが増える
こうした変化に加えて、水をよく飲むようになることがあります。
②ー4その他の病気・要因
次のようなものも原因になります。
✅ 肝臓病(代謝異常で水分バランスが崩れる)
✅ 子宮蓄膿症(メス猫:発熱・多飲が見られることがあります)
✅ 薬の影響(ステロイド、利尿剤など)
「いつもと違うな」と感じたら、早めの相談が安心です。
受診の目安|病院で相談した方がいいサイン

「このくらいなら様子見でいいのかな?」
迷いますよね。
次のような変化が見られた場合は、早めの受診をおすすめします。
受診をおすすめするチェックポイント
✅ 水を飲む量が急に増えた
✅ おしっこの回数・量が増えている
✅ 食欲が落ちてきた
✅ 体重が減っている
✅ 口の中の臭いが強くなった
✅ 元気がない、寝てばかりいる
これらは「体のどこかに異常がある」サインです。
特に高齢猫や持病がある猫は、早期発見が重要です。
自宅でできるケアと予防法

水をたくさん飲むこと自体は、悪いことではありません。
大切なのは「自然な水分補給」なのか「異常な多飲」なのかを見極めることです。
そのために、おうちでできる工夫をご紹介します。
水分をとりやすくする工夫
✅ ウェットフードを取り入れる
ドライより水分が多く、自然に水分を摂れます。
✅ 複数の場所に水皿を置く
猫は気分で飲む場所が変わります。
キッチン・リビング・寝室などに分けるのがおすすめです。
✅ 循環式の給水器を活用する
流れる水を好む猫も多く、飲水量アップにつながることがあります。
清潔な環境を保つ
✅ 水皿は毎日洗う
✅ トイレも清潔にして、排尿量の変化に気づきやすくする
✅ フードや水は新鮮に(直射日光を避ける)
清潔な環境は、病気予防の基本です。
健康チェックを習慣に
病気の多くは、初期では分かりにくいことが多いです。
✅ 年1〜2回の健康診断(特に7歳以上)
✅ 体重・食欲・トイレの変化をこまめに観察
✅ 「なんとなく元気がない」は早めに相談
まとめ

水をよく飲むのは“体からのメッセージ”です
猫が水をよく飲むこと自体は、悪いことではありません。
でも、「急な変化」や「他の症状」があるときは要注意です。
✅ 一時的なら自然な生理現象のこともある
✅ 慢性腎臓病や糖尿病などが隠れている場合もある
✅ 飲水量・おしっこ・元気・食欲の変化を観察することが大切
✅ 不安を感じたら、早めに動物病院で検査を
日々の小さな変化に気づけるのは、毎日そばにいる飼い主さんだけです。
「いつもより少し違うかも?」という違和感を見逃さず、
愛猫の健康を守る行動につなげていきましょう。
よくある質問(FAQ)

Q1. 猫が水をよく飲むのは、どれくらいから「多飲」ですか?
正常な飲水量の目安として、体重1kgあたり40〜60ml/日が基準になります。
ただしフード(ウェット/ドライ)や季節で変わるので、
「以前より急に増えたかどうか」を重視してください。
Q2. 水をよく飲んで、おしっこも増えています。様子見でいいですか?
多飲と多尿がセットで出るときは、腎臓病や糖尿病などの可能性があります。
元気に見えても初期のことがあるので、早めに検査をおすすめします。
Q3. 病院に行く前に家でできることはありますか?
まずは飲水の1日量で計ってみましょう。
トイレの回数、尿の量、体重、食欲の変化もメモしておくと診察がスムーズです。
可能なら、普段使っているフードの種類(ドライ/ウェット)も伝えられると安心です。