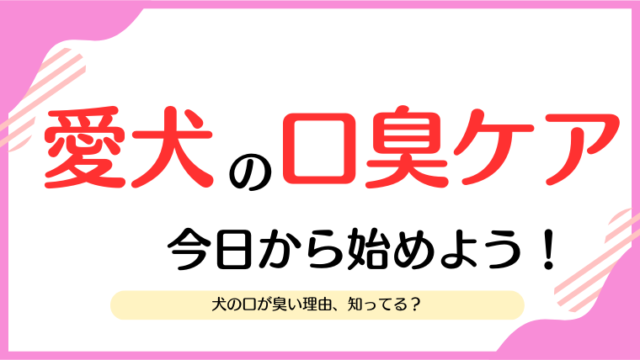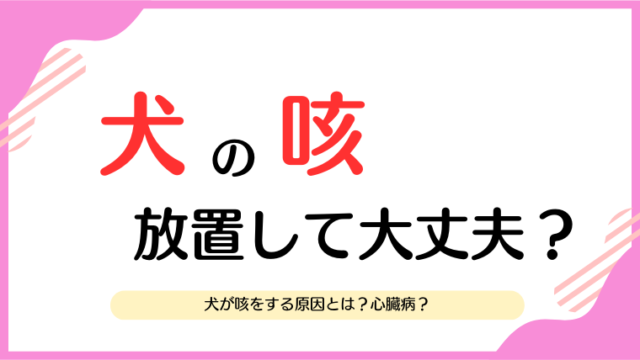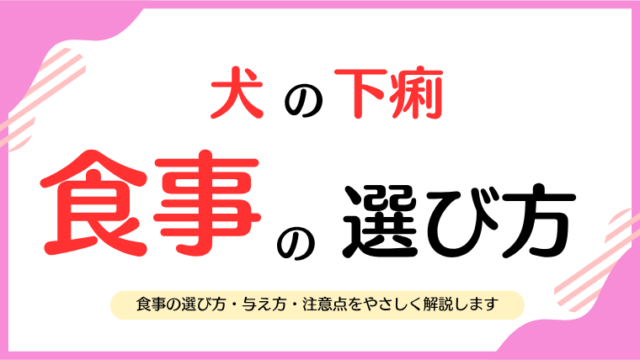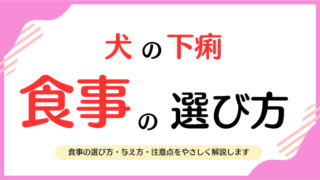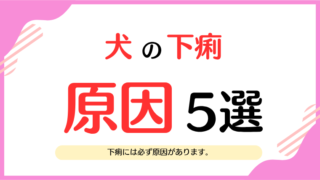犬の便に血が混じっていると、飼い主としてはとても不安になりますよね。
「どこか痛いのかな?」
「すぐ病院に行くべき?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
血便は、犬の体からの重要なサインです。
今回は、血便の種類や原因、適切な対応について、獣医師の視点からわかりやすく解説します。
飼い主として正しく判断できるように、一緒に学んでいきましょう。
血便には2種類ある|色の違いを見逃さないで

血便といっても、実は2つのタイプがあります。
それぞれ意味が異なり、見た目で見分けることができます。
鮮やかな赤色の血が便についている場合
これは「鮮血便(せんけつべん)」と呼ばれます。
肛門に近い場所、大腸や直腸などで出血している可能性があります。
便の表面や、おしりを拭いたティッシュに赤い血がつくのが特徴です。
比較的軽い炎症や、硬い便による小さな傷が原因のこともありますが、腫瘍や重度の腸炎の可能性もあるため、注意が必要です。
黒っぽい便に血が混じっている場合
こちらは「黒色便(こくしょくべん)」と呼ばれます。
胃や小腸など、体の奥で出血が起こった場合に見られるものです。
血液が消化酵素によって分解され、タールのように黒くなります。
これは緊急性の高い症状で、胃潰瘍や異物による出血など、命にかかわる病気が隠れていることもあります。
すぐに病院を受診しましょう。
血便の主な原因とは?|症状から読み解く

では、血便が出る原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下に、よくある5つの原因を紹介します。
1. 食べ物やストレスによる腸の炎症
急なフードの変更や、拾い食いが原因になることがあります。
また、旅行や引っ越しなどのストレスも腸に負担をかけます。
腸の粘膜が荒れると、出血を起こしやすくなります。
一時的なものであれば自然に治ることもありますが、繰り返すようであれば要注意です。
2. 寄生虫や細菌感染
子犬によくあるのが、寄生虫による腸炎です。
回虫や鉤虫などが腸内に寄生し、粘膜を傷つけて出血を引き起こします。
また、サルモネラやカンピロバクターといった細菌も血便の原因になります。
下痢や嘔吐をともなうことが多く、感染症のリスクもあるため、早めの診察が必要です。
3. 異物や骨などの摂取
固い骨や異物を飲み込んだ場合、腸や胃を傷つけて出血することがあります。
便に混じる血は黒くなることが多く、吐き気や食欲不振も見られます。
内視鏡やレントゲンで確認し、場合によっては手術が必要になることもあります。
4. 腸の腫瘍やポリープ
高齢の犬では、腫瘍が原因の出血も見られます。
特に大腸や直腸にできるポリープやがんは、便の表面に鮮血がつくのが特徴です。
初期症状が少ないため、定期的な検診が重要です。
早期に発見できれば、外科的な治療で改善が期待できます。
5. 抗生物質や薬剤の副作用
薬の副作用として腸の粘膜が荒れ、出血するケースもあります。
特に抗生物質を長期で使った場合、腸内のバランスが崩れやすくなります。
薬を使っていて血便が出たときは、必ず獣医師に相談しましょう。
血便が出たときの正しい対応|慌てず観察と相談を

血便を見つけたとき、まず飼い主ができることは「落ち着いて観察すること」です。
以下のポイントをチェックしてみましょう。
観察するポイント
– 血の色(鮮やか?黒っぽい?)
– 血の量(少し?多い?)
– 便の状態(柔らかい?水様?)
– 他の症状(食欲は?元気はある?吐いていない?)
このような情報は、病院での診断にも役立ちます。
可能であれば便を持参し、ビニール袋に入れて病院へ行きましょう。
写真を撮っておくのもおすすめです。
すぐに受診すべきケース
以下のような場合は、早急な受診が必要です。
– 黒色便が出た
– 下痢や嘔吐が続く
– 元気や食欲がない
– 血便が何度も出る
とくに子犬や高齢犬は、体力が落ちやすく危険です。
「様子を見よう」で手遅れになる前に、病院で診てもらいましょう。
血便の予防と日常ケア|健康な腸を守るために

血便を防ぐには、日ごろの体調管理が欠かせません。
以下のポイントを意識してみましょう。
毎日の食事は「消化にやさしいもの」を
急なフード変更は、腸に大きな負担をかけます。
新しいフードに変えるときは、1週間ほどかけてゆっくり移行しましょう。
また、人の食べ物を与えるのも避けましょう。
犬には犬用の栄養バランスが必要です。
散歩中の拾い食いを防ぐ
道ばたのゴミや落ちている食べ物には、細菌やウイルスが潜んでいることがあります。
「口に入れそうだな」と思ったら、すぐ声をかけて制止しましょう。
「拾い食い防止トレーニング」も有効です。
定期的な検便・健診を受ける
寄生虫や腫瘍などは、早期発見が大切です。
年に1回の健康診断に加え、便のチェックもおすすめします。
特にシニア犬は半年ごとに健診することで、病気の予防につながります。
おわりに|血便を見逃さない目を持とう

血便は、犬の体からのSOSサインです。
「少しだから大丈夫」と思っていても、重大な病気の前触れかもしれません。
大切なのは、毎日の様子をよく観察し、小さな変化に気づくこと。
そして、迷ったら早めに相談することです。
飼い主さんの気づきが、愛犬の命を守る第一歩になります。
不安なときは、いつでも動物病院へご相談くださいね。